この記事では、任意整理後に滞納した場合のリスクと対処法について解説します。
滞納とは文字通り支払いが滞ることを言いますが、これが任意整理“後”となるとまるで重みが違ってきます。
通常の借り入れの滞納なら遅延損害金が発生したり取り立ての連絡が来る程度ですが、任意整理後の滞納となると即座に一括請求を命じられる(=分割払いの終了)リスクが発生します。
それをさらに放置すると、最悪の場合財産の差し押さえに発展することになりますので『無視(放置)だけは絶対にしてはいけない』というのが大原則になります。
この記事を読んでいただければ、
- 任意整理後の返済の仕組み
- 任意整理後に滞納するリスク
- 任意整理後に滞納した場合の対処法
といったことが学べます。
それではどうぞ!
任意整理後の返済の仕組み
まず大前提として、任意整理を代理人(=法律事務所)に依頼していることが条件です。
※なぜ法律事務所なのかという部分は別記事で詳しく解説します。
-320x180.jpg)
任意整理の契約が締結すると、以下の流れで進行していきます。
- 受任通知の送付(=債権者からの取り立てが停止)
- 債権者への返済が一時的に停止する(約6ヶ月間)
- 弁護士費用を分割返済
- (和解交渉終了後)返済スタート
ここで注意したいのが、債権者への返済が停止したからといって支払いは停止しないということです。
停止期間を利用して支払う費用を積立金とも呼ばれますが、この費用は弁護士費用の分割払いに利用されるだけでなく和解交渉を有利に進めるための交渉材料としても活用されるので、とても大事な役割を担っています。
-320x180.jpg)
積立金の支払いを滞納すると、、、
任意整理の依頼料(弁護士費用)を分割払いする際は積立金から充てられますので、滞納が続けば任意整理の和解交渉が一向に進まないという状態に陥ります。
さらに滞納が続けば契約自体が無効(=解約)になりますので、期日厳守で支払いに努めるようにしましょう。
ボーダーラインは“2ヶ月連続”
借金の滞納は1ヶ月遅れなら問題ないケースがほとんどですが、2ヶ月連続で滞納すると金融事故(ブラックリスト)となります。
積立金や後ほど解説する任意整理後の滞納期間についても、2ヶ月連続滞納すると契約の無効や取り立ての再開といったように悪影響を及ぼすことになります。
このように、金融界隈においては“2ヶ月連続滞納”というのが悪影響のボーダーラインになるケースが多いので覚えておきましょう。
任意整理前と後に滞納した場合のリスクを比較
任意整理前と後で滞納するリスクを比較した場合、行き着く先が「財産の差し押さえ」という部分では一緒ですが、そこに至るまでの流れに“差”があります。
任意整理“前”の滞納~財産差し押さえまでの流れ
任意整理前は以下のような流れで進行していきます。
- 督促状や取り立ての連絡がくる(=遅延損害金の発生)
- (①からおおよそ1~3ヶ月後)差し押さえ予告通知書(催告書)が届く
- 裁判所から通知(支払督促)が届く
- (③からおおよそ1~3ヶ月後)裁判
- 財産の差し押さえ執行
貸金業者によっても変動しますが、最初の督促状(①)から財産差し押さえ(⑤)に発展するまでにおおよそ3~6ヶ月程度かかる計算になります。
ただ滞納期間が長くなればなるほど任意整理の交渉条件も厳しくなりがちですので、自力返済が困難になった時点で早めに相談することが大切です。
任意整理“後”の滞納~財産差し押さえまでの流れ
任意整理後も滞納が続くと財産没収という点では一緒ですが、明確に2ヵ月連続で滞納した時点で一括請求(=分割返済の終了)の流れになります。
任意整理前は「2回分まとめて払えばいいや」が通ったかもしれませんが、任意整理後は甘い考えは通用しませんので、覚悟を持って任意整理に臨みましょう。
-320x180.jpg)
任意整理後の滞納が続いた場合の対処法
任意整理後に滞納が続いた場合、または1回でも滞納する恐れがある場合は、早めに代理人へ相談することが大切です。
一番やってはいけないのが「何もせず放置すること」。
放置したところで取り立てや督促状は止まりませんし、行き着く先は財産没収(差し押さえ)です。
さらに代理人からの連絡も無視すると、契約不履行と判断され代理人を降りる(=委任契約の解約)リスクも発生しますので、放置は百害あって一利なしです。
では滞納した場合どう対処すべきなのか、以下にまとめました。
- 任意整理の再和解
- 追加介入
- 他の債務整理を検討
任意整理の再和解
任意整理の再和解とは、一度債権者と行った和解交渉を再度行う方法になります。再和解が成立すれば、返済期間が延びたり、更なる減額に繋がり月々の返済計画が楽になるメリットがあります。
追加介入
追加介入とは、任意整理で除外してた債権者を追加で手続き(和解交渉)する方法です。任意整理する債権者を増やせば、それだけ負担も減るので返済に回せるお金も捻出することが可能です。
ただ、逆を言えば「除外していた整理対象がなければ無意味」とも言えます。
他の債務整理を検討
再和解、追加介入でも解決しない場合は他の債務整理を検討する必要があります。
自己破産・個人再生は任意整理と違い「裁判所の認可」が必要になります。裁判所を通すということは、相応の手間と時間、お金もかかる上、財産の差し押さえも覚悟する必要があります。
あくまで最終的な手段であると心得て、そうならないための努力は怠らないようにしましょう。
まとめ|任意整理後は2回連続の滞納に注意
任意整理後に滞納した場合のリスクと対処法について解説しました。
まとめますと、
- 任意整理後は2回連続で滞納すると一括請求のリスクがある
- 対処法は「再和解」「追加介入」「他の債務整理を検討」の3種類に分かれる
- 任意整理後の滞納はすぐ代理人に相談することが大切
任意整理後は計画通りに返済を続けることが理想ですが、何らかの理由や事情で返済が滞る可能性も出てくるかもしれません。その時、「すぐ代理人に相談するのか」または「現実逃避するのか」で結果はガラリと変わります。
はたしてどちらが正しいのか、、は言うまでもありませんよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
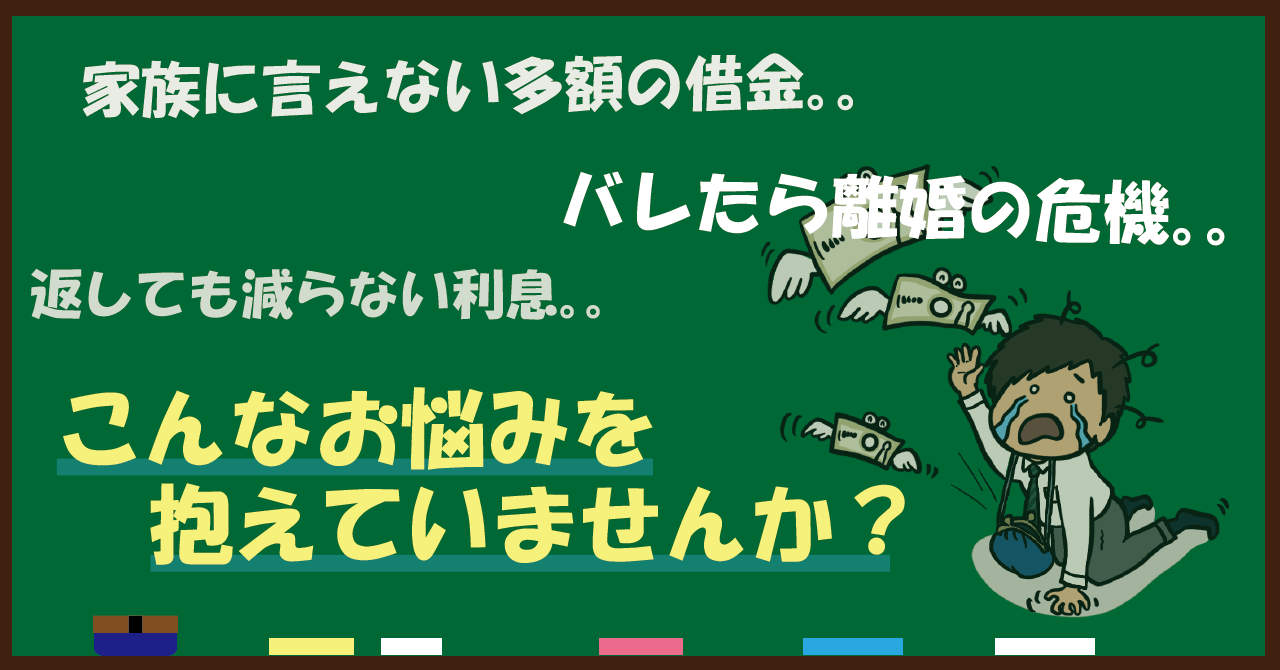
家族に内緒で借金完済できる“唯一”の方法、それは任意整理(にんいせいり)です。
愛する家族だからこそ言えない借金の悩み、それに畳みかけるかのように迫る返済の期日、山積みの督促状、取り立ての着信履歴の数々。。
現実逃避をしたくなる気持ち、よーく分かります。
なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
私がオススメする弁護士法人ユア・エース(旧:天音総合法律事務所)は、無料・匿名で利用できる借金減額診断ツールがありますので、まずは減額できる可能性があるのかどうかを確認してみましょう。
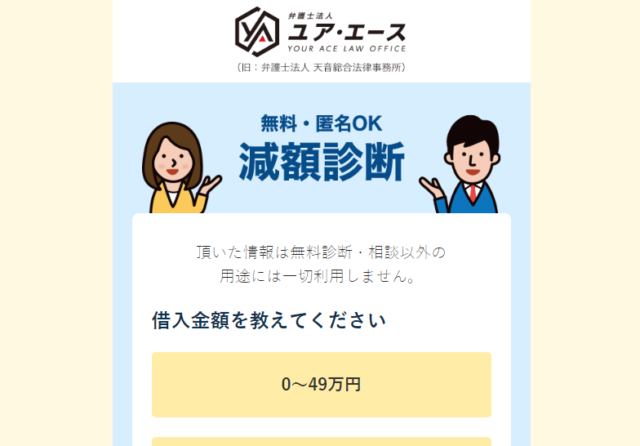
\3つの質問に答えるだけ/


.png)
.png)

-640x360.png)
-640x360.jpg)
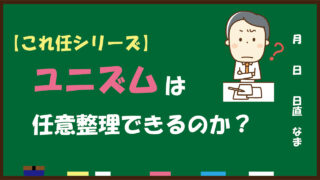
-150x150.png)