この記事では、任意整理でいくらまでの借金を手続きできるのかについて解説します。
任意整理は自力での返済が困難になった場合の救済措置ですが、それがいくらまでの借金なら手続きできるのか疑問が残ります。
借金額が10万円の人もいれば50万円、200万、500万 etc、、、人によって様々です。
基本的には債務額の上限というものはありませんが、金額以上に支払い能力が大きく関係してきます。
この記事を読んでいただければ、
- 債務額と支払い能力の関係性
- 任意整理の下限と上限について
- 借金額がいくらなら任意整理した方がいいのか
といったことが学べます。
それではどうぞ!
任意整理はいくらから(下限)~いくらまで(上限)という制限はない
結論から言うと、任意整理にいくら~いくらまでといった“金額的な制限”はありません。
任意整理は代理人と債権者の間で和解(減額)交渉を行い、お互いの合意の下で将来利息がカット(または減額)される手続きのため、減額後も返済を続けていくことには変わりありません。
そのため、減額後の借金を3~5年で完済できるだけの収入を持ち合わせていることが大前提となります。
支払い能力の計算式
では何を基準に支払い能力の有無が判断されるかと言うと、下記の計算式を用いるのが一般的です。
≪支払い能力の計算式≫
[債務額(万円)]÷[36~60(ヵ月)]
≒任意整理後の毎月の返済額(万円/月)
※和解交渉次第で減額の割合が変動するので「≒」と記載しています。
※債務額は減額後を想定して利息抜きの債務額で計算します。
基本的には代理人と債権者の間で返済計画が確定するので、債務者が「○年で返済希望」と要望することはできませんが、「毎月○万円で返済希望」と希望返済額を伝えることは和解交渉における大切な要素となります。
1つ例を紹介します。
例)債務額200万円、毎月の希望返済額4万円の債務者Aの場合、
200(万円)÷60(ヵ月)=3.3(万円/月)
→5年以内で完済できる見込みがある(=支払い能力がある)ので和解交渉が成立しやすい
上記のように、希望返済額の範囲内であれば支払い能力はあると判断されるので和解交渉が成立しやすくなります。
逆のパターンも見てみましょう。
例)債務額500万円、毎月の希望返済額6万円の債務者Bの場合、
500(万円)÷60(ヵ月)=8.3(万円/月)
→最大の5年でみても返済に毎月8.3万円必要になるので和解交渉が成立しない(=支払い能力がない)
この場合だと、返済見込額に対して希望する返済額が下回っているため支払い能力がないと判断される(=任意整理は難しい)ということになります。
多重債務(借金地獄)が任意整理検討の目安
一概に「○万円以上で任意整理すべき」という基準があるわけではありませんが、もし現時点で多重債務(=借金地獄)に陥ってる場合は検討することをオススメします。
さらに滞納が続けば利息の上乗せや遅延損害金の発生、最終的には債権者から訴えられて給与・財産差し押さえ、なんてことにも。。
そうなってからでは遅いので、借金地獄に陥る段階で将来利息や遅延損害金をカットできる任意整理を検討しましょう。
10万円以下の任意整理は逆に高くつくことも
例)借金10万円(年利18%)で3年で返済を計画している場合、
利息=元金×利率×借入期間÷365なので、
100,000(円)÷018×1095(日)÷365=54,000(円)が利息となる。
というように債務額が少額(10万円以下)だとカットした金額と同程度もしくは逆に高くつく可能性もあるので、自力で返済した方がいい場合もあることを覚えておきましょう。
※「利息って何だっけ?」という方は、別記事(↓)にて詳しく解説しております。
-320x180.png)
支払い能力があっても任意整理できないケース
任意整理にいくら~いくらまでといった制限はなく支払い能力が条件と解説しましたが、下記の場合だと支払い能力があっても任意整理できないケースがあります。
- 支払い回数が極端に少ない
- ブラックリストを許容できない
- 既に訴えられた後で強制執行が発動している
支払い回数が極端に少ない
借り入れやローンを組んでまだ間もない、もしくは滞納を繰り返していて支払い回数が極端に少なかったりすると任意整理に応じてくれないケースがあります。
まずは通常の返済を続けて支払い能力がある“証拠”を残すことが重要で、それが難しい状況であれば任意整理ではなく自己破産・個人再生を検討しましょう。
ブラックリストを許容できない
任意整理の手続きを行うと、完済後5~10年は事故情報、いわゆるブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載ると、
- 新規の借り入れ
- クレジットカード作成
- 各種ローン商品(カーローンやショッピングローン等)
- その他分割決済を伴う商品・サービス
上記ような審査を介する商品(サービス)を受けることができなくなります。
既に訴えられており強制執行が発動している
滞納にも段階があり、
- 督促状や取り立ての連絡がくる
- 一括請求(分割支払いの終了)
- 訴訟(支払督促)
- 給与・財産の差し押さえ
大まかに4段階で進んでいきます。
給与・財産の差し押さえ執行が開始されると任意整理ができなくなるだけでなく、会社や自宅にも通知が届き、完済に向けて「毎月の給与の1/4」「住宅や車などの財産」などが強制的に没収されてしまいます。
そうなる前に早めの段階で法律事務所に相談するようにしましょう。
※債権者に訴えられた場合の流れについて、別記事(↓)で詳しく解説しております。
-320x180.jpg)
司法書士は1社あたりの債務額が140万円を超える場合代理人になれない
1社あたりの債務額が140万円を超える場合、司法書士は代理人になることができません。
他にも訴訟に発展した場合簡易裁判所までしか対応できない等、弁護士事務所と比べると職務の制限が発生してしまうことは否めません。
もしそういう事案が発生した場合は、新たに弁護士事務所に依頼する必要がありますので、最初から弁護士事務所に依頼するというのも一つです。
まとめ|任意整理はいくらではなく支払い能力の有無
任意整理はいくらまでの借金を手続きできるのかについて解説しました。
まとめますと、
- 任意整理に上限(下限)はない
- 債務額に応じた支払い能力が求められる
- 支払い能力があっても任意整理できないケースもある
まずは債務額がどれくらいあるのかを把握し、自分の収入でいくらまでの返済額を許容できるのかを算出してみることが第一歩になります。
任意整理だけが全てではありませんので、自分の債務額・支払い能力にマッチした債務整理を検討してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
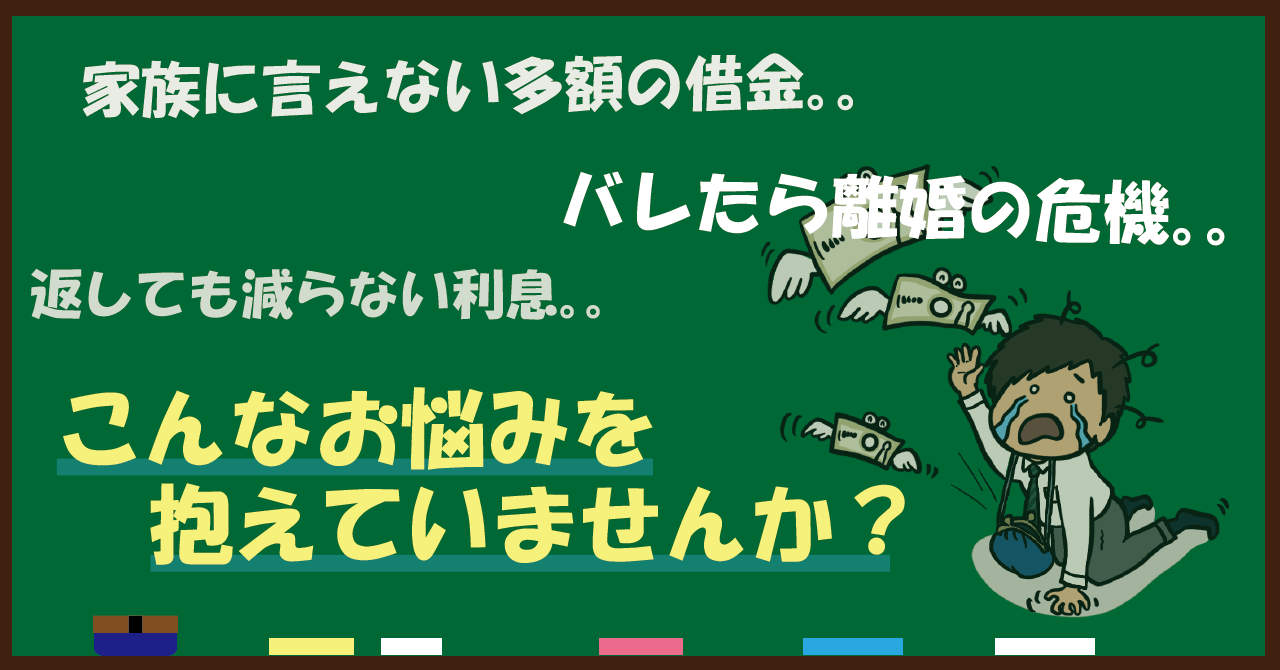
家族に内緒で借金完済できる“唯一”の方法、それは任意整理(にんいせいり)です。
愛する家族だからこそ言えない借金の悩み、それに畳みかけるかのように迫る返済の期日、山積みの督促状、取り立ての着信履歴の数々。。
現実逃避をしたくなる気持ち、よーく分かります。
なぜなら筆者である私自身がまさにこの状況だったからこそ、です。
私がオススメする弁護士法人ユア・エース(旧:天音総合法律事務所)は、無料・匿名で利用できる借金減額診断ツールがありますので、まずは減額できる可能性があるのかどうかを確認してみましょう。
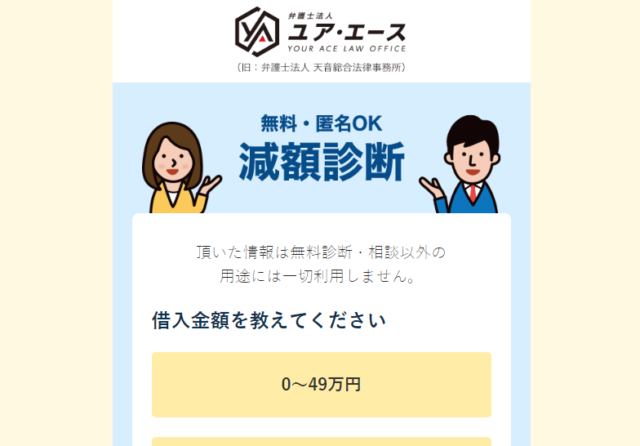
\3つの質問に答えるだけ/
.jpg)

.png)
.png)
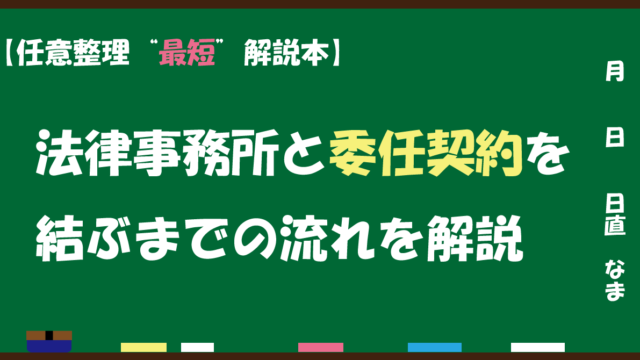
-640x360.jpg)
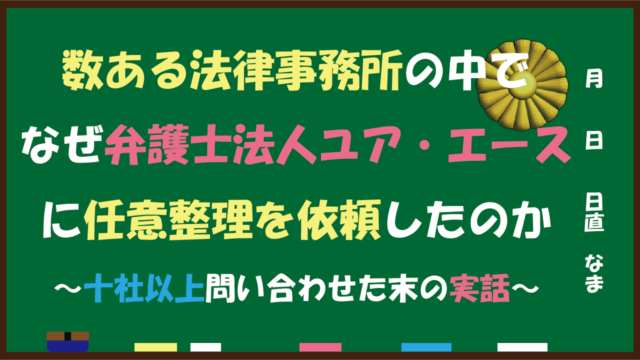
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-150x150.png)